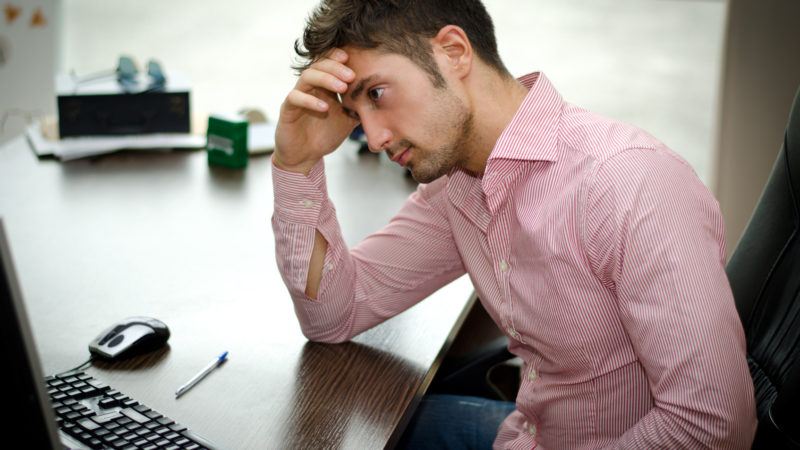日大のクライシスマネジメントの失敗 – 悪質タックル事件

2018年5月6日。日本大学と関西学院大学とのアメリカンフットボールの試合で、悪質なタックルが問題になりました。
対応は後手後手に回り、まずは悪質タックルをした学生が記者会見で謝罪し、そのあとから監督やコーチが記者会見にのぞみ、両者は釈明に追われました。問題が提起されてからは、とくにテレビのワイドショーで追求が始まっていました。
関学大が日大の悪質タックルに気づいたのは試合の翌日でした。しかもSNSを通じて外部からの指摘を受けてだったのです。動画を撮られていたのです。試合を観戦した個人によってユーチューブにアップされ、それをツイッターで視聴するようにと誘導発言されていたのです。
関学大は、改めてビデオで試合を確認して、悪質タックルがあったことに気がつきます。動画は、朝日新聞のツイッターアカウントや、スポーツジャーナリストのM氏などが取り上げ、問題提起が始まりました。不祥事はSNSからマスコミによる報道へと類焼し、炎上は拡大していきました。
危機管理の始動の出遅れが痛かった
日大アメフト部として、いや日本大学という学校組織として、炎上する前の動画がアップされた段階で、クライシスマネジメント(危機管理)をスタートさせておかなくてはならなかったのです。
学生が謝罪してから、監督やコーチが釈明。これは順序が逆の対応です。
事態を甘くみたことも被害を拡大
「たかがSNSだ。火は消えるだろう」「スポーツ部の問題だ。大学組織は関係ない」「学生個人に謝らせれば済む」。こうした考えが、日本大学というブランドに傷を負わせてしまいました。
組織の中の個人が、組織全体が、どう行動し、どう発言しなければならないのか。それを改めて考えさせてくれる事件でした。(浦山明俊)