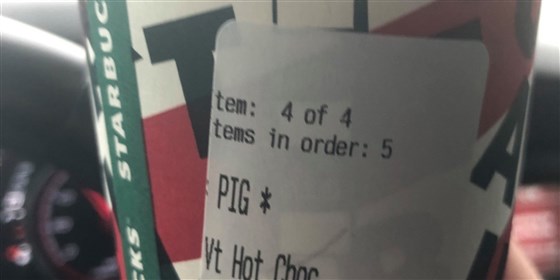コンテンツマーケティング記事の見出しはどうあるべきか

かつての紙の時代の記事の見出しづくりは、熟練を積んだ職人的なスキルが必要でした。なぜなら、限られた文字数(スペース)に収める必要があったためです。最小限の文字数で収めるための数々のスキルが必要だったのです。
現代のオンライン記事の時代はどうでしょうか。文字数を数える必要性は、なくなりました。数えなくても、画面上で自由に削除したり修正したりできるからです。けれども、限られた文字数で最大効果の見出しをつくるという感覚は生き続けるべきです。
与えられた情報で、いかにして効果的な見出しをつくればよいでしょうか。以下の3つのコツを参考にしてください。
1.企業にとってのそのコンテンツの目的を決める
コンテンツマーケティングにおいては、すべてのコンテンツは企業の目的を果たすために存在しています。その目的を明確化する必要があります。たとえば、メールを開かせること、訪問者を増やすこと、記事のクリック数を上げること、SEO効果を高めることなどです。目的が複数あっても問題はありません。最も重要なものを特定した後、最適な見出しを作成します。さらに、二番目、三番目の目的に適った別の見出しを使うことができるなら、それらもつくったほうがよいでしょう。
2.読者層を特定する
コンテンツはだれでも見ることができますが、本当に見てほしい読者(オーディエンス)はだれですか? そう尋ねると、多くの人は「ターゲットは、流行、に敏感な20~30代の男女です」とか、「ペルソナは、子供がいる30~40代のワーキングウーマンです」などと答えるかもしれません。けれども、こうしたターゲットは、幅が広すぎるため、有効な見出しをつくる際にはあまり有効ではありません。企業がコンテンツを発信する目的を思い出し、きわめて狭いオーディエンスを特定する必要があります。たとえば、「企業の人事担当者」ではなく、「工場労働者の離職率を減らす方法で悩んでいるメーカーの人事部課長」などと特定するのです。
また、企業がコンテンツマーケティングをおこなう目的が、「オンラインニュースレターをターゲットにクリックして開いてもらうこと」だとします。であれば、タイトルでメールを開いてもらわなければなりませんから、そこで購読者に対して直接話しかける必要があります。つまり、そのコンテンツが購読者にどんな利益をもたらし、好奇心を刺激するかを考えつつ、魅力的な見出しを作成する必要があります。
もし、コンテンツマーケティングの目的がSEOである場合、読者のほとんどはあなたの会社の商品・サービスのことをよく知らない人でしょう。その場合、SEOに焦点を当てて見出しを作成するならば、商品・サービスではなく、読者がもともと持っている関心や悩みからスタートする必要があります。
3.読者がこのコンテンツを読む理由を想定する
読者がそのコンテンツ記事に惹きつけられ、読みたくなる原因、フックはなんでしょうか?あるいは、どう思われたら、記事を読むのをやめてしまうのでしょうか?読者にとって必要なのは、ビジネス上有益な情報でしょうか?娯楽でしょうか?毎日の生活上の実用性でしょうか? 読者にとって、それを読む理由がなければならないということです。
グーグルの検索結果ページを例にとって考えてみましょう。多数の結果が表示されている場合、ある特定の記事をクリックする理由はなんでしょうか?もちろん、すべての見出しが同じであれば、読者は上に表示されたものから順番にクリックするでしょう。しかし、あなたの記事の見出しが際立っていれば、下位にあってもクリックされる可能性が高くなります。(高橋 眞人)